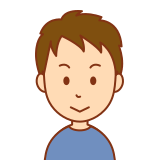
EVは一回の充電でどれくらい走れるの?
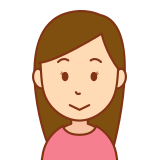
カタログのどの数字をみたらいいの?
電気自動車を満充電にして、どのくらいの距離を走ることができるのか。気になりますよね。
カタログに書いてある、「一充電走行距離km」でみればいいのでしょうか?
半分、正解です。
それ以外にも、カタログには「交流電力量消費率kWh/km」、「駆動用バッテリー容量kWh」も書いてあるので、それらからも走行可能距離kmが計算できそうですよね。
カタログのどの数字をみたらいいのか、以下に解説していきます。
一充電走行距離とは
一充電走行距離とは、バッテリーを満充電にした状態で走行できる最大距離を指します。ガソリン車の「航続距離」に相当し、EVのカタログで最も注目される数値の一つです。
この数値は、WLTCモード(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle)という国際的な試験方法に基づいて測定されますが、実際の走行条件(運転方法、エアコン使用、路面状況、外気温など)によって変動します。
実際に走れるかどうかは走行条件で変わりますが、満充電でどれだけ走れるのかを見るには、この「一充電走行距離」を参考にするといいです。
交流電力量消費率とは
交流電力量消費率は、EVの燃費を示す数値で、「電費」とも呼ばれます。
具体的には、1km走行するのに必要な電力量を表し、単位はWh/km(ワットアワー・パー・キロメートル)です。
この数値が小さいほど電費が良い(少ない電力で長く走れる)ことを意味します。ガソリン車の燃費(km/L)とは逆で、数字が小さいほど優れていると覚えておくと良いでしょう。
この数値は、試験パターン走行できなくなった(=一充電走行が終了した)ところのバッテリーを満充電するのに必要な交流充電電力量Whを、一充電走行距離kmで割って求めます。
駆動用バッテリー容量とは
駆動用バッテリー容量とは、EVに搭載されているバッテリーが蓄えられる電気の総量を指します。
単位はkWh(キロワットアワー)で、この数値が大きいほど多くの電気を蓄えることができるため、より長く走行できる可能性が高まります。EVの価格にも大きく影響する要素です。
日産サクラは満充電でどのくらい走れるのか
以上でみてきたように、EVの「どれだけ走れるか(一充電走行距離)」は、「どれだけ電気を蓄えられるか(駆動用バッテリー容量)」と「どれだけ効率よく電気を使えるか(交流電力量消費率)」によって決まる、という関係にあります。カタログの数値はあくまで目安ですが、これらの関係を理解することで、EVの走行性能をより深く把握することができます。
たとえば、日産サクラを例にとってみてみましょう。
日産サクラXのカタログには、
・一充電走行距離(WLTCモード) 180km
・交流電力量消費率(WLTCモード) 124Wh/km
・駆動用バッテリー総電力量 20kWh
とあります。
駆動用バッテリー総電力量(kWh)と交流電力量消費率(Wh/km)から導き出される航続可能距離は、
駆動用バッテリー総電力量(kWh)/交流電力量消費率(Wh/km)=20×1000/124≒161km
になります。一方、一充電走行距離は180kmです。
なぜ値が異なるのでしょうか?
カタログに記載されている「一充電走行距離」「駆動用バッテリー容量」「交流電力量消費率」の数値が、単純な割り算でぴったり合わないのは、いくつかの理由が考えられます。
1.バッテリーの使用可能容量とカタログ値の違い
カタログに記載されている駆動用バッテリー容量(例えば20kWh)は、バッテリー全体の総容量です。しかし、実際にはバッテリーの劣化抑制や安全性の確保のため、全容量を100%使い切ることはありません。バッテリーマネジメントシステム(BMS)によって、実際に利用できる容量は、表示されている総容量よりも少なくなっています。この「使用可能容量」が計算のベースとなるため、カタログ値の総容量で計算するとズレが生じます。
2.回生ブレーキによる回生エネルギー
EVは、減速時にモーターを発電機として利用し、運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに充電する「回生ブレーキ」の仕組みを持っています。カタログの交流電力量消費率は、走行中に消費する電力量を示していますが、この回生によって得られたエネルギーは考慮されていません。つまり、走行中に消費したエネルギーの一部が回生によって回収されるため、単純な割り算では実際の走行距離と合わなくなることがあります。
EVやHEVでよく聞く”回生”とはなんでしょうか。簡単にまとめのでこちらもご覧ください↓
EVは満充電でどのくらい走れるのか
EVが満充電でどのくらい走れるのかは、カタログの「一充電走行距離」でみるのが妥当です。
ただし、半分正解といったのは、実際はそこまで走れないことが多いためです。
カタログにある「一充電走行距離」も「電力量消費率」も、ある決められた走り方(最近はWLTCモード)での値です。
WLTCモードとはどんなモードでしょうか? 簡単にまとめましたのでご覧ください↓
実際にEVを運転している方ならご存じのとおり、ドライバーがどのような走り方をするか、温度含めた環境条件、道路が登りなのか下りなのか、エアコン動作がどうなのかで大きく変わってきます。
運転スタイルや環境条件によって燃費が変わるのは、ガソリン車についても同じです。皆さんの運転の仕方で変わってくるのでカタログ燃費(電費)の数字にはどうしてもとどかないことが多いと思います。
よく言われるのは、
・カタログの数字の6割ぐらい
・冬場に暖房入れるととたんに走行可能距離表が半分に
・・・
ふつうのガソリン車に乗っている人からすると、なにそれって感じですが、自分の運転スタイルや慣れてくればだんだん読めてくると思います。
ですので、EVでもメータなどにバッテリー残量や残り航続距離が表示されたりしますが、慣れないうちはカタログの一充電走行距離や電力量消費率をあまり信用しないで、余裕をもって充電行動をとったほうがいいでしょう。
JARI(日本自動車研究所)の解説です。~「WLTPにおける電気自動車の一充電走行距離および交流電力量消費率試験法」|JARI Research Journal 20221011~

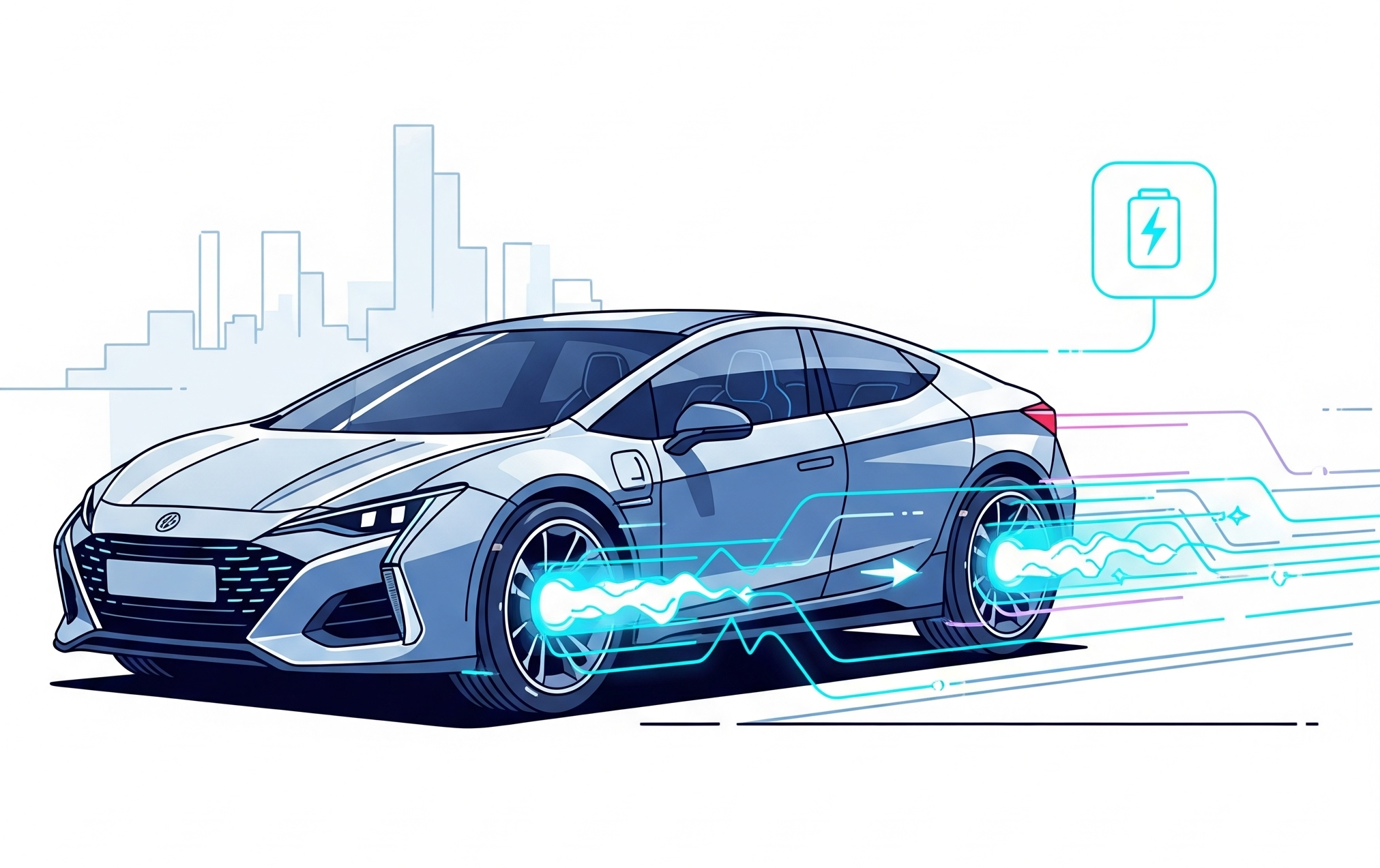

コメント